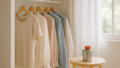心に残るスローガンの作り方|やさしく学べる実践ガイド
スローガンの重要性を理解しよう
スローガンとは何か?その定義と役割
スローガンは、ブランドやサービスの想いを短い言葉で伝えるフレーズです。ふだんの会話よりも簡潔で、誰が見ても同じイメージが浮かぶことが大切。たとえば「毎日を軽やかに」は、商品名を知らなくても「暮らしをラクにするものかも」と想像できます。スローガンの役割は主に、①ブランドの方向性を示すコンパス、②広告やサイトの共通言語、③社内外をつなぐ合言葉の三つ。名刺、Webサイト、SNS、パッケージなど、触れる場所が増えるほど親しみが育ちます。長い説明は読まれにくい時代だからこそ、ひと目で伝わる言葉が出会いの入口になります。さらに、発表直後だけでなく日々使い続けることで、読み手の心に少しずつ定着し、自然に「このブランドといえば、あの言葉」と記憶の引き出しに入っていきます。
なぜスローガンが必要なのか?
商品が多い市場では、似た特徴が並びます。そこで差がつくのは、伝え方。スローガンは、選ばれる理由をひと息で伝える装置です。検索画面やSNSのタイムラインで数秒しか見られなくても、短い言葉なら届きます。さらに、チームの判断軸にもなります。新しい企画や投稿案に迷ったら「この言葉に合っている?」と確認でき、ブレが減ります。読み手側にも「自分に向けられている」と感じてもらいやすくなり、ブランドとの距離が近づきます。ショップカードや梱包に添えるメッセージとしても活躍し、小さな接点に温度を加えてくれます。結果として、広告費の大小に左右されず、覚えてもらう仕組みが積み上がっていきます。
スローガンがビジネスに与える影響
印象に残るフレーズは、口コミや紹介の言い回しにも使われます。「あの店は◯◯って言ってたよ」と自然に広がり、説明しなくても伝わる資産になります。また、採用やパートナー探しにもプラス。価値観を短く示せるので、共感してくれる人が集まりやすくなります。オンライン広告や紙ものを作る際も、基準があると制作がスムーズ。無数の案から迷わず選べ、納期の短縮にもつながります。さらに、長く使うほど歴史が重なり、ブランド年表の要(かなめ)に。創業ストーリーや商品改良の歩みと結びつき、記念日やキャンペーンでも活躍します。言葉は小さいけれど、働き方と届け方を整える力がある
——それがスローガンの大きな価値です。
スローガン制作の基本ステップ
ターゲットオーディエンスを明確にする
まず「誰に届けるのか」を一人の人物像まで具体化します。年齢層や生活リズム、よく使う言葉、週末の過ごし方、よく見るメディアなどを想像し、その人が嬉しくなる表現を探します。たとえば忙しい朝に使う商品なら、ゆっくり読ませるより「パッとわかる安心感」を優先。手帳に残したくなる短さ、口に出しやすい音の並びを意識します。ペルソナのメモは短くてOK。「名前・職業・好きなこと・最近の小さな悩み」を書くだけで、言葉の方向が定まります。
メッセージを簡潔にまとめる方法
次に、ブランドの約束を一文に凝縮します。
- 「理想の未来」を名詞で書く(例:やさしい毎日)。
- 「方法」を動詞で足す(例:選んで整える)。
- 余分な語を削る(指示語や重複表現)。
この順で削っていくと、短くても温度のある言葉になります。五七調や三三七のテンポを試すのもおすすめ。声に出して読んだとき、息継ぎしやすい長さになっていれば合格です。
競合分析を行う意義
似た領域のブランドがどんなフレーズを使っているかを観察し、言い回しの重なりを避けます。キーワードが同じでも、視点をずらせば個性が出ます。たとえば「時短」が多いなら「段取りを楽しく」へ。「上質」が多いなら「手に届くごほうび」へ。かぶらない表現は覚えられやすく、検索時の混同も減らせます。
言葉選びのポイント
読みやすい日本語を選び、漢字・ひらがな・カタカナの配分を整えます。硬い語彙より、口に出しやすい響きを優先。末尾は名詞止め、またはやわらかい動詞でまとめると品よく仕上がります。英語やフランス語を入れる場合も、読み間違えのない表記に。数字は少なめにして、視覚的な美しさを大切にしましょう。
心に届くスローガンの特徴
短くて覚えやすいフレーズ
音数はおおよそ5〜12文字程度が扱いやすい範囲。長くなる場合は二拍に分け、前半で価値、後半で情緒を置きます。たとえば「暮らし、軽やかに」。句点や読点を活用すると、視線のリズムが整います。濁音・半濁音の配置、繰り返し(リフレイン)も記憶に残りやすい工夫です。
感情を喚起する要素
ストーリーの入口になる言葉を選びます。「いつも」「そっと」「もう一歩」など、日常の温度を含む副詞は親しみを生みます。視覚イメージ(光、香り、手触り)を想像できる名詞を入れると、頭の中で情景が広がります。
例:
・今日をそっと軽くする
・ひとさじの、ときめき
・わたしに合う、ちいさな選択
ブランドと一致するテーマ性
ブランドの価値観とスローガンは一体です。理念・商品・接客・発信のどれかだけが浮いてしまうと、読み手は迷います。社内で合意し、使う場面を具体的に決めておくと、どんな人が伝えても同じ印象に。ビジュアル(色・余白・写真)との相性も確認し、世界観を統一しましょう。
スローガン作成の実践例
成功したスローガンの事例紹介
ここでは仮の例でイメージをつかみましょう。
- ライフスタイル雑貨:「朝を、やさしく。」 —— 朝時間の体験を想像させる一言。
- オンライン学習:「一歩ずつ、わたしペース」 —— 学びの安心感を端的に。
- ハンドメイドブランド:「日々に、手の温度」 —— 手仕事の価値を視覚化。
いずれも短く、使う場所を選びません。タグライン、見出し、梱包メッセージにも展開しやすく、声に出したときの心地よさがあります。
もっと伝わるように整えるヒント
最初の案が長いときは、不要な修飾を外して主語と述語を近づけます。対義語で締めるより、前向きな言葉で終えるとやわらかい印象に。似た案が複数あるときは、第一印象の残り方、口に出すリズム、印刷したときの見え方を基準に選びましょう。言い換えの例:
・「毎日をもっと便利に」→「毎日、軽く」
・「高品質な日用品」→「日々に、上質」
・「だれでも簡単」→「わたしにも、すぐ」
スローガンをテストする方法
A/Bテストの実施方法
候補を2〜3案に絞り、期間を決めて比較します。Webサイトのヒーロー画像や広告バナー、SNSのプロフィール文にそれぞれの案を掲出し、反応の違いを見ます。クリック数や保存数だけでなく、コメントの言い回しやDMで寄せられる質問の傾向も参考になります。表示回数が少ないと差が見えにくいので、同条件になるよう露出をそろえましょう。
フィードバックを活用する
社内だけでなく、実際のユーザーにも短いアンケートを取り、読んだときに浮かぶ情景・気持ち・連想ワードを書いてもらいます。専門用語は避け、感じたことをそのまま書ける設問に。迷ったときは「どの言葉なら友人に勧めるとき使いたい?」と聞くと、本音に近づけます。受け取った声は付箋にして壁に並べ、頻出ワードを拾い、言い回しを整えます。
スローガン管理と更新の方法
長期的な視点での見直し
スローガンは季節の合図のように、時々メンテナンスすると鮮度が保てます。年に1回、使った場所・役立った場面・誤解が生まれやすかった表記などを振り返り、微調整を検討しましょう。歴代の案やボツ案も保管しておくと、キャンペーン用に活用できます。社内マニュアルに「使ってよい場・避けたい場」を明記しておくと、担当が変わっても安心です。
市場環境に合わせて変えるタイミング
新カテゴリの展開、主要顧客の変化、大きなデザイン刷新など、節目が来たら更新のサイン。とはいえ、急に全変更するより段階的に切り替えるほうが読み手にやさしい場合も。半年ほど重ねて使い、検索やSNSでの呼称が落ち着いてから一本化するとスムーズです。アーカイブ記事には旧フレーズを残し、歴史として楽しめるようにしておくと、ファンの愛着も守れます。
まとめと次のステップ
自分のビジネスに合ったスローガン作成への取り組み
ここまでの流れは、人物像 → 一文化 → 言い回し調整 → テスト → 運用というシンプルな道のり。大切なのは、読み手の毎日に寄り添う視点です。今日からできることとして、①ペルソナの短いメモ作り、②候補フレーズを10個書く、③声に出して3つに絞る、の3ステップから始めましょう。
さらなるリソースと学びの紹介
言葉の引き出しを増やすには、キャッチコピーの書籍や名作の見出し集を手元に置くと便利です。広告年鑑、雑誌の表紙、駅のポスターなど、生活の中の言葉をスクラップしておくと、表現の幅が広がります。発音しやすい音の並び、母音の心地よさ、語尾の柔らかさにも注目してみてください。
スローガンづくりに役立つツール
- 音数カウンター:文字数と音のリズムを確認。
- 連想語辞典:近い言葉・やさしい言い換えを探すときに。
- 付箋アプリ:案の並べ替えやチームでの検討に。
道具はシンプルで十分。大切なのは、読み手の心に寄り添うことです。あなたの言葉が、だれかの一日をふわっと明るくしますように。